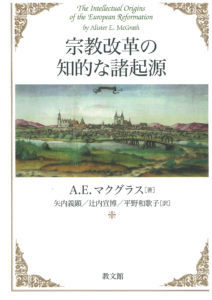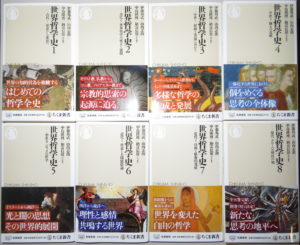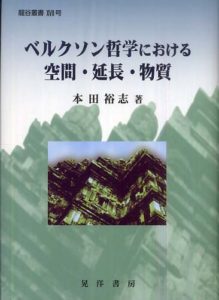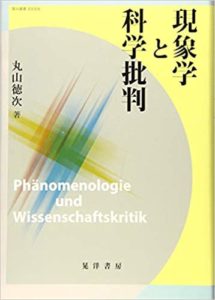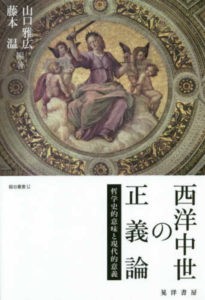松田克進先生(本学文学部教授・龍谷哲学会委員)が訳者の一人となって翻訳された、ピエール=フランソワ・モロー『スピノザ入門[改訂新版]』が、2021年5月に白水社から刊行されました。以下は、出版社からの紹介です。(他に、【特別寄稿】スピノザは二度、日本を語る。 ピエール=フランソワ・モローさん(哲学史家)という記事もあります)。
〈内容説明〉
スピノザ評伝の決定版!
伝説ぬきのスピノザ像を浮き彫りにした評伝
十七世紀の哲学者がいかに生き、論じ、受容されたのか。改訂新版ではスピノザが『神学政治論』で日本について言及した箇所も考察する。
「スピノザの生涯と著作は、これまで、多くの伝説によって物語られ、多くの偏った解釈に捻じ曲げられ、多くの誤解に晒されてきた」(第一章より)。
十七世紀の哲学者スピノザが、いかに生き、何を書き、論じ、どうのように受けとめられてきたのか。本書は、当時の時代状況やオランダの特異性を紹介するとともに、蔵書目録およびテクストにみられる引用からスピノザの語学力や教養の限界までも探る。
改訂新版では、著者による日本語版のためのあとがき「暴露するものとしての日本」を掲載。スピノザが『神学・政治論』のなかで日本について言及したテクストを考察する。スピノザが生きた時代の日本は、スピノザにとってどのような役割を果たしたのか。
〈伝説抜きのスピノザ像を描く〉評伝の決定版。
[著者略歴]
ピエール=フランソワ・モロー Pierre-François Moreau
1948年生まれ。高等師範学校を卒業。1992年までソルボンヌ大学で教鞭を執り、現在、リヨン高等師範学校・文学人文科学部門名誉教授。現代フランスを代表する哲学史家の一人。PUFから刊行中の新スピノザ全集Spinoza-Œuvresの責任編集者で、その第四巻『エチカ』の仏訳を担当。
[訳者略歴]
松田克進(まつだ かつのり)
1991 年京都大学大学院博士後期課程単位取得退学、哲学専攻。龍谷大学文学部教授。主要著訳書に、『スピノザの形而上学』(昭和堂、2009 年)、ドミニク・フォルシェー『年表で読む 哲学・思想小事典』(共訳、白水社、2001 年)がある。
[訳者略歴]
樋口善郎(ひぐち よしろう)
1991 年京都大学大学院博士後期課程単位取得退学、哲学専攻。大阪学院大学非常勤講師。主要論文に、「ヘーゲルと貧困問題」(関西哲学会年報『アルケー』第24 号、2016 年)、主要訳書に、ベルナール・ブルジョワ『ドイツ古典哲学』(共訳、白水社文庫クセジュ807 番、1998 年)がある。
〈目次〉
序
第一章 スピノザの生涯
Ⅰ 事実関係
Ⅱ スピノザの伝記の典拠
Ⅲ 誕生地アムステルダム
Ⅳ ユダヤ人とマラーノ
Ⅴ スペインおよびポルトガルの遺産
Ⅵ 体制と軋轢
Ⅶ 教育・絶縁・環境
Ⅷ コレギアント派とソッツィーニ派
Ⅸ デカルト主義
Ⅹ 神学と政治学
ⅩⅠ 晩年
ⅩⅡ スピノザの教養
ⅩⅢ 熱狂と伝説
第二章 著作
Ⅰ 『知性改善論』
Ⅱ 『神、人間、および人間の幸福に関する短論文』
Ⅲ 『デカルトの哲学原理』と『形而上学的思想』
Ⅳ 『神学・政治論』
Ⅴ 『エチカ』
Ⅵ 『国家論』
Ⅶ 『ヘブライ語文法綱要』
Ⅷ 『書簡集』
Ⅸ 真作でないテクスト、散逸したテクスト
第三章 主題と問題
Ⅰ 人物
Ⅱ 場所
Ⅲ 原理
Ⅳ 解釈上の争点
(一)無神論
(二)唯物論
(三)決定論と自由意志
(四)神秘主義
第四章 受容
Ⅰ 『神学・政治論』への批判
Ⅱ 実体の単一性
Ⅲ スピノザの影響
Ⅳ 汎神論とカバラ思想
Ⅴ 新スピノザ主義
Ⅵ 汎神論論争
Ⅶ ドイツ的伝統
Ⅷ 十九世紀フランス
Ⅸ 文学者による読解
Ⅹ 精神分析
ⅩⅠ 十九世紀と二十世紀のユダヤ教
ⅩⅡ 二十世紀文学
結び
日本語版のためのあとがき 暴露するものとしての日本
訳者あとがき(旧版)
訳者あとがき(新版)
参考文献③(訳者による)
参考文献②(原書による)
参考文献①(原注による)
人名索引

以上です。
 2021年7月20日に、知泉書館から、上智大学中世思想研究所編『「原罪論」の形成と展開――キリスト教思想における人間観――』が出版されました。
2021年7月20日に、知泉書館から、上智大学中世思想研究所編『「原罪論」の形成と展開――キリスト教思想における人間観――』が出版されました。