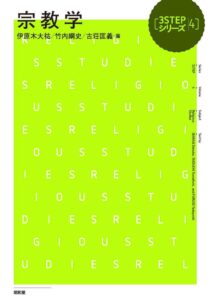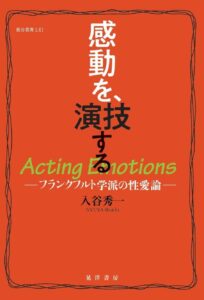【新刊紹介】松田克進(2023)『スピノザ学基礎論 スピノザの形而上学 改訂版』、勁草書房。
龍谷大学文学部の松田克進教授(龍谷哲学会会員)が、2023年5月に勁草書房から、『スピノザ学基礎論 スピノザの形而上学 改訂版』を出版しました。
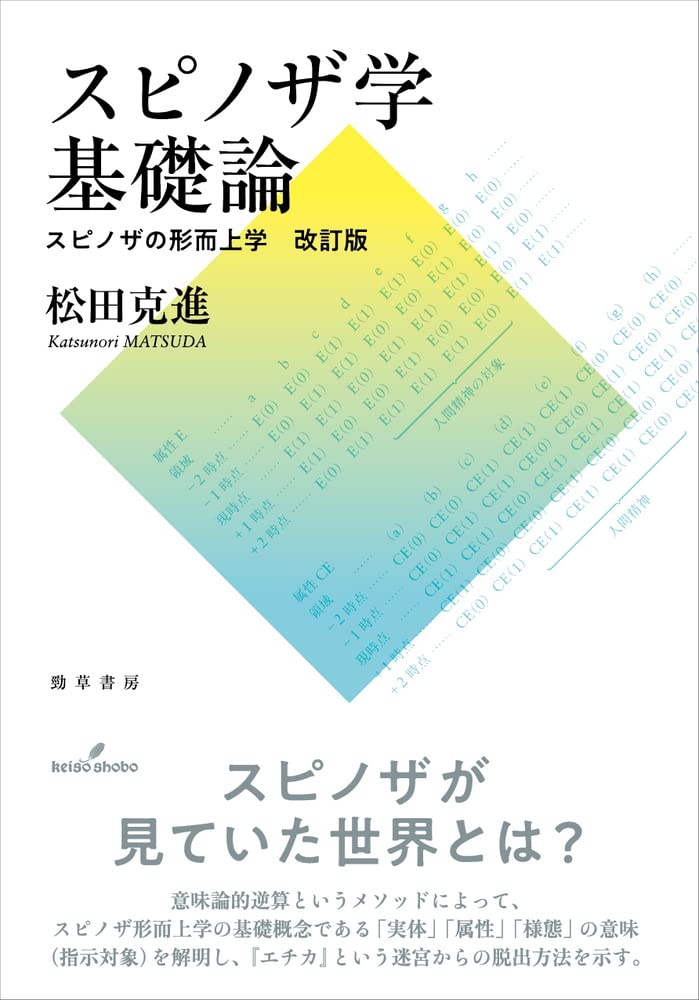
出版社による同書の内容説明は以下のとおりです。
「多面的なスピノザ思想を読解するために──『エチカ』は前から順に読み進めても理解できない。第1部に出てくる基本概念の意味論的種明かしが第2部の頭で行われるからである。本書は、ここを集中的・徹底的に分析し、『エチカ』の基本概念かつスピノザの世界像の基礎・土台・根底でもある「実体」「属性」「様態」を明らかにする」。
同書の内容説明は以上のとおりです。
同書は、副題からも分かるように、松田教授が2009年6月に昭和堂から出版した『スピノザの形而上学』の改訂版になります。
どのような改訂が本書に施されているか、また本書がどのような特徴のある研究書であるかは、出版社から公開されている同書の「はじめに」からも確認できます。
関心をおもちの方は、ぜひご覧になってください。
以上です。