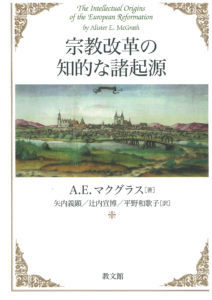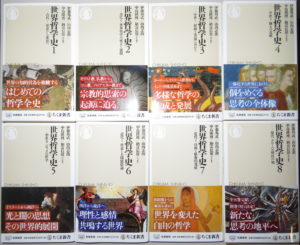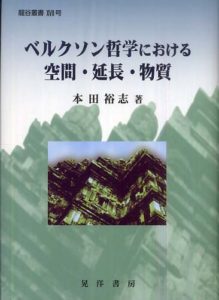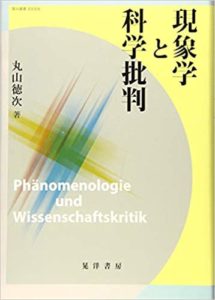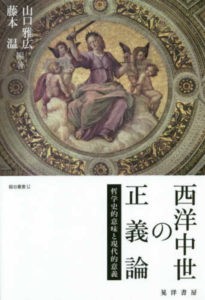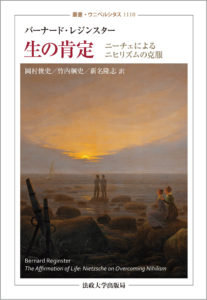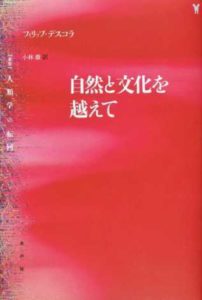小林徹先生(本学文学部講師・龍谷哲学会委員)が翻訳された、フィリップ・デスコラ『自然と文化を超えて』が、2020年1月に水声社から刊行されました。
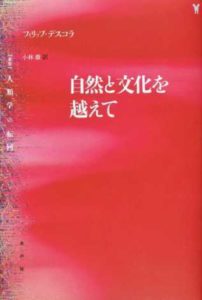
以下は順に同著の内容紹介、目次、デスコラの略歴になります。
ぜひ手に取ってみてください。
内容紹介
アチュアル族のインディオとの出逢いをきっかけに、地球規模で広がる四つの存在論を横断し、非人間をも包摂する関係性の分類学を打ち立てる――。
近代西洋が発明した「自然/文化」という二分法を解体し、人類学に“転回”をもたらした記念碑的著作。(本書帯より)
私たちは野蛮ではない状態を文化と呼び、文明化されていない状態を自然と呼ぶ。しかし、自然と文化が対立する二つの項であるということはそれほど自明だろうか。フィリップ・デスコラによれば、この分断を遂行したのは近代西洋だけである。ここには、西洋と非西洋を隔て、人間と非人間を本質的に切り離して考える近代西洋特有の思想(ナチュラリズム)が認められるのだ。ところが、世界や環境について思考する仕方は他にも存在する。肉体的差異を認めつつ、人間と非人間を本質的に同質の霊魂を持つ存在と捉えるアニミズム。人間と非人間を内面的にも肉体的にも似たような存在と考えるトーテミズム。連続する無数の差異の中に人間と非人間の差異を織り込み、両者の照応関係を打ち立てるアナロジズム。世界の正しい捉え方を決定する唯一のモデルなど存在しない。私たちは、世界の中で世界の見方を作り上げ、変換し続けているのである。綿密な現地調査と膨大な文献に基づいて論証を進め、人類学における〈存在論的転回〉を象徴する一冊となった本書が行きつくのは、世界に対する真に開かれた思考である。
目次
第1部 「自然」の騙し絵(連続体の諸形象/野生と家庭/大分割)
第2部 経験の構造(実践の図式/自己との関係/他者との関係)
第3部 存在の配置(アニミズム再考/存在論としてのトーテミズム/ナチュラリズムにとって確かなこと/アナロジーの眩暈/項・関係・カテゴリー)
第4部 世界の用法(集合の創設/習俗の形而上学)
第5部 関係の生態学(繋がりの諸形態/霊魂の交渉/構造の歴史)/可能事の目録
著者紹介
デスコラ,フィリップ[Philippe Descola]
1949年、パリに生まれる。文化人類学者。
サン=クルーの高等師範学校を卒業後、クロード・レヴィ=ストロースに師事し、社会科学高等研究院で教鞭をとる。
現在、コレージュ・ド・フランス教授
以上です。(訳者からいただいた「内容紹介」を追記しました(2020年2月7日))。